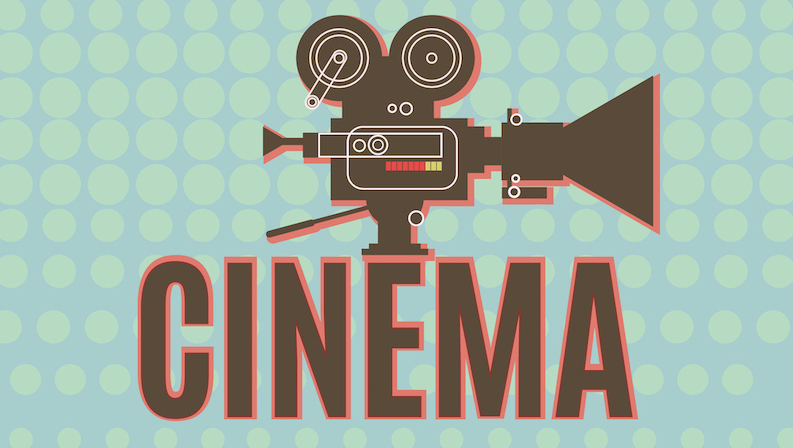中国、毛沢東の文化大革命時代にバレエの英才教育を受けたリー・ツンシンの半生。
青年期になり、国の期待を一身に背負いアメリカに短期バレエ留学をすることになったリー。
そこで、リーは初めて「自由」を知る。
国に戻らなければならない時、独断でアメリカ人の恋人と結婚し、アメリカに残ることを決めるリー。
しかし、それは国を捨てること、家族を捨てることを意味していた。
邦題は「小さな村の小さなダンサー」とやんわりしているが、原題は「MAO’S LAST DANCER」(毛沢東の最後のダンサー)なんですよね。
このニュアンスの違いはおもしろい。
邦題を決める権利は、契約によって、製作者だったり配給会社だったり、場合によって様々らしい。
これは日本側が決めたんだろうか。
「ちょっとインパクト強すぎるから、ここは少しやんわりいこうか」とね。
内容は、MAO’S というほどマオマオしていなかったので邦題くらいでちょうど良かったような気もする。
リーを演じる青年たちが、現役のバレエダンサーで、見応えがあった。
ただ、「半生」という映画にはありがちだが、半生を2時間に収めるのだから、やはり薄っぺらくなってしまう部分も否めない。
こんなことがありました、そしてこんなことがありました、というような。
アメリカ人のガールフレンドと結婚するところなんかも、そこまで二人の濃密さは描かれていないのに、結婚(後に破局)したような印象もあり、永住権との兼ね合いからも、なんだかちょっと軽い…?と思ってしまった。
でも年表を見たら、結婚はリーが二十歳の時なんですね。
それは軽いというより、勢いとか国への反発とか、そんな理由で無鉄砲に動いてしまっても非難できないかもしれない。
最近はノーベル賞の中国の反発問題で、国を出た中国人民主化運動家たちがテレビに映る機会も多かったけれど、知性があり世界を知った中国人が自国の独裁政権を冷やかで悲しい目で見つめているのをみると、「中国人」というくくりで中国人を語るのはナンセンスだと思うし、そんな民主化運動家たちがいつか中国を変える力を持つときがくるのではないか、という一縷の望みを感じたりもする。
しかし、最近の目覚ましい中国の発展を快く思っている中国人たちは、国力に自信を持ったり(つまりは国家を称賛)しているから、中国人同志でもかなりの温度差がある。
前に話した中国人は「困るほど自由がないわけでもないし商売だってできる。現状に満足している」と言っていた。
抑えつけられていると感じている中国人ばかりではないのだ。
なんていうか、臭いものに蓋をしていても、それが臭ってこなければいいという人が多いように思う。
早くその壺の中身が発酵して爆発するのを見たい。
なんてね。毒。